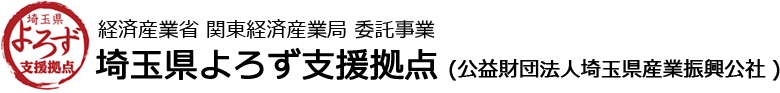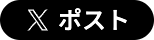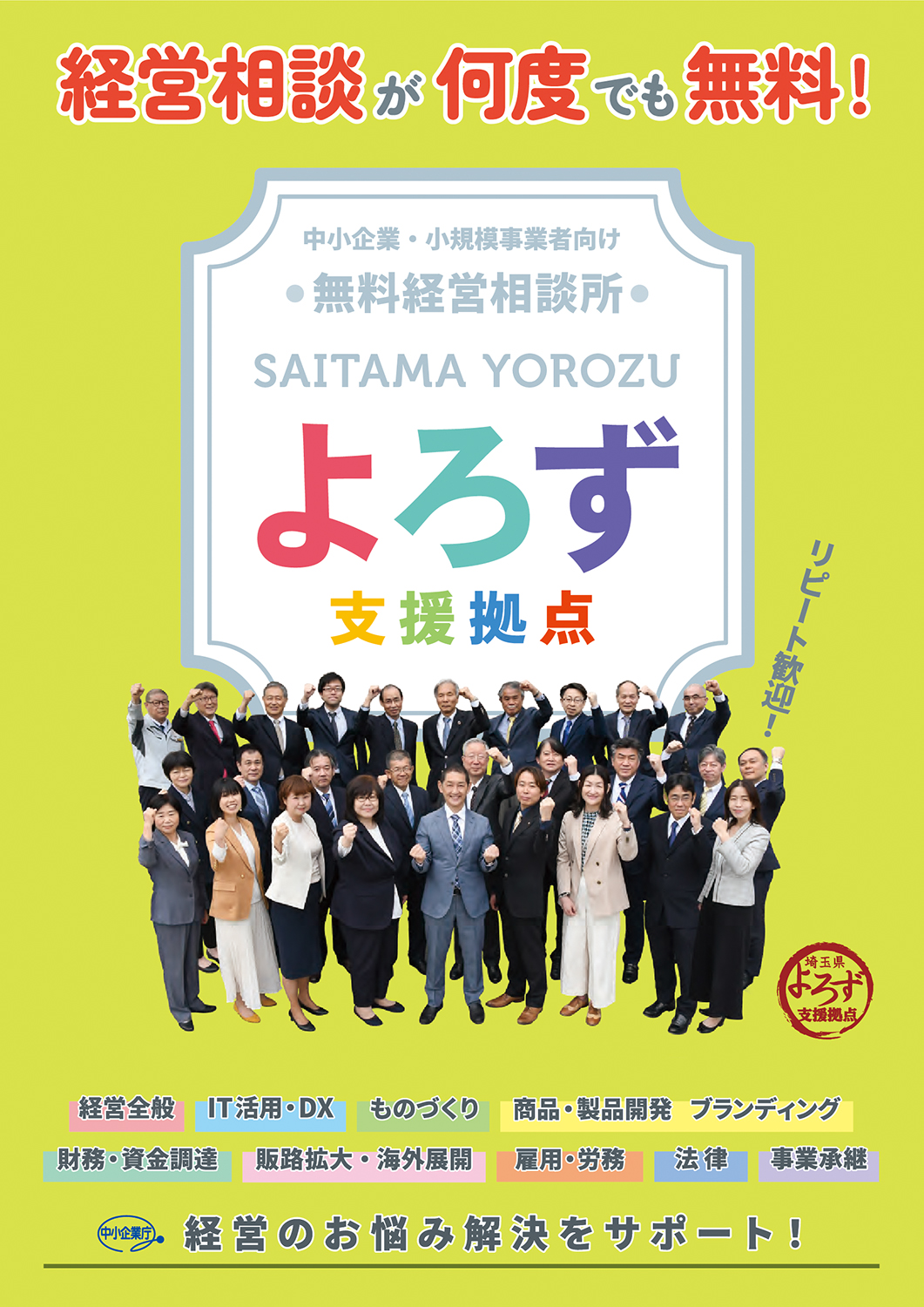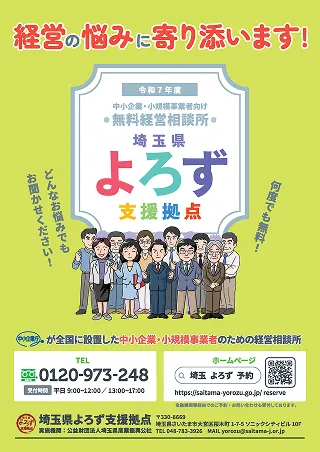東立製作所
- 支援内容:
- 生産性向上
- 業種:
- 製造業
- 代表者名
- 松川 晃代
- 住所
- 本社 埼玉県朝霞市三原2-30-3
日高工場 埼玉県日高市旭ヶ丘690-1

IoTと原価管理で生産性と収益性を改善
社員とともに歩む100年企業への道
原価が見えず赤字案件も
IoT活用と生産性向上を目指し支援を要請
昭和35年創業の東立製作所は、工業用プラスチックの切削加工を中心に事業を展開する。埼玉県日高市に工場を置き、合成樹脂やプラスチックの切削、接着、溶接、曲げ、組立、射出成型を行う。高度な品質管理体制で顧客のニーズに応え、医療・食品・ポンプ・自動車・電子・半導体など多様な分野に製品を供給。社会インフラの根幹を支える重要な役割を担っている。

日高市の工場

高精度・高品質・量産加工など幅広いニーズに対応

樹脂素材の加工等試作品から接着・組立・量産まで
同社は多品種少量および量産のいずれも対応可能な生産体制を強みとし、月1500件規模の受注に対応している。しかしその一方で、製品別の原価や収益性を正確に把握できていないことが課題だった。原価管理の改善を目的に数年前からIoTを導入していたものの、エラーが頻発するなど当初想定した運用ができず、効果的に活用できていなかった。
「製品の種類が多く、どの製品が利益を出しているのか把握できていませんでした。なかには作れば作るほど赤字になるものもあり、原価管理の必要性を感じていましたが、自分たちだけで進めるのはハードルが高かったです。生産管理システムを入れ替えるなど試行錯誤もしましたが、うまくいきませんでした。数字に基づいた経営判断ができないことが一番の不安でした」と松川社長は振り返る。
このような状況に加え、外注費や間接費の負担も重く、さらに売上の約50%を大手顧客1社に依存するリスクも抱えていた。生産性向上とIoTの活用のために専門的な知見が不可欠と判断した松川社長は、埼玉県よろず支援拠点への相談に踏み切った。
IoTの安定稼働と原価管理の精緻化へ
数値の見える化で新たな課題が浮き彫りに
埼玉県よろず支援拠点では、メーカー出身の3名のコーディネーターがチームを組み、各々の専門性を活かして支援を進めた。提案の際は、工程・人員配置・設備構成などの実態に即した継続可能な仕組みの構築を重視。教科書どおりのやり方を伝えるのではなく、メンテナンス性や現場の負荷を考慮した詳細な検討が行われた。
全体統括のコーディネーターは、IoTや原価管理などの個別テーマに対して、常に「東立製作所が最終的にどうなりたいか」という経営的な目的を確認しつつ、論議が枝葉末節に偏らないよう全体の方向性を調整した。
IoTを活用した在庫量の調整においては、すべての製品を対象とするのではなく、パレートの法則に基づき、利益貢献度の高い主要量産品から着手する方針を提案。これにより、早期に成果を見える化し、社内定着を促進した。
原価管理においては、当初から実施されていた労務費・機械経費の区分に加え、水道光熱費・消耗品費・地代家賃・保険料・修繕費などの共通経費をさらに分解・整理するよう提言。その結果、製造原価報告書の精度が高まり、間接費の配賦根拠が明確化された。
各専門コーディネーターが担当する個別支援を統合しつつ、企業全体の改善ストーリーを構築。松川社長の感覚的な不安を、数値と根拠に基づく経営課題として可視化し、具体的なアクションへと導いた。

コーディネーターとのミーティング

相談者と村野幸哉CO(右から2番目)
IoTに精通しているコーディネーターは松川社長の説明と現場確認を通じて、通常は1工程につき1つのRFIDタグを読み取るべきところ、複数のRFIDタグを同時に読み取る必要があるという特殊な要件がエラーの原因と指摘した。そして、RFIDの安定稼働を目指し、現場に立ち会い、アンテナの角度や設置位置の検証、電波取得の実験を段階的に実施し試行錯誤を重ねた。
難易度の高い技術を要するため、ソフトウェア会社や商社に、サーバの処理性能やシステム連携の改善を求めるよう助言。改善を進めるにあたり、代表製品や一部工程から試行し、効果を実感することにより社内定着が図られるようにした。松川社長は社内で関係者と調整しながら実装を進めた。

アンテナの角度やタグ位置を微調整し正確な稼働データ取得

人名や設備名、工順の各カードの中にタグが貼られている
原価管理については、製造原価報告書や決算データを確認する中で、配賦の基準が数十年前の指数のまま使われていることを把握。さらに、共通材料費や検査・仕上げ・洗浄といった間接経費の処理が曖昧で、実態と乖離した原価計算が行われていることも明らかになった。
原価管理担当のコーディネーターは製造原価報告書や決算データを基に勘定科目を「機械負担・人負担・共通」に区分。減価償却費や修繕費の配賦比率を明確化し、NC・MC・汎用機ごとの時間単価を設定、労務費は直接工の作業時間を基準に算出した。勘定科目の分類や配賦案は、「なぜこの配賦なのか」を経営者自身が説明できるまで議論を重ねた。
管理方法として既存システムをExcelで補完するハイブリッド運用を提示し、メンテナンスの負荷も視野に入れた現実的で継続可能な仕組みを構築。まずは主要製品から着手し、成果と運用ノウハウを蓄積して全体に展開した。その結果、外注比率の高さや内製化の余地、段取り替えのボトルネック、価格交渉の必要性といった新たな課題も浮き彫りになり、さらなる改善に向けた取り組みを進めるきっかけとなった。公的機関や商談会情報も紹介し、支援は原価管理に留まらず、販路拡大へと広がっていった。

現場と一体となって改善に取り組む
「自分たちではどうにもならない状況になり相談したところ、専門のコーディネーターの方を紹介していただき、問題解決へ導いてくださいました。コーディネーターさんは経営のコンサルタントのように、どんな内容でも時間をかけて道筋を示してくださる心強い存在です。常に寄り添い、伴走し、全方位で相談に応じてくれる埼玉県よろず支援拠点は、私たちにとって非常に頼もしい存在です。本当に助かっています」と松川社長は話す。
生産性向上と価格転嫁により収益性改善、
新市場進出でさらなる成長へ
生産性と収益性の向上を目指し、IoTと原価管理の改善に取り組んだ同社。改善を重ねた結果、設備の稼働状況をリアルタイムで可視化できるようになり、設備休止時間は60%削減され、稼働率が向上した。これにより生産量の増加と残業・外注費の削減が進み、生産性は大きく向上した。IoTも現場に定着し、社員が稼働率を意識して行動するようになった。原価管理では製品ごとに採算を数値で把握できるようになり、主要顧客への価格転嫁を実現した。新規顧客に対しては原価データを反映させ、収益性改善に繋げている。支援開始から付加価値率は27%増加。数字に基づく経営が定着し、社員の行動も変わり始めている。

稼働データを共有しながら意見交換する社員たち

段取り改善が進み、設備稼働率が大幅に向上
「社員全員が同じ方向を向き、若手も『一人前になりたい』という思いで取り組んでいます。自主的にCAD/CAMを学んだり、会議で稼働率や原価の数字を語る姿も増えました。その思いに応えられるよう、時間をかけて土台から成長できるように支えていきたいと考えています。将来の 『100年企業』の実現に向け、次の世代へ続く会社をつくっていきたいと思っています」と松川社長は未来への展望を語る。積み重ねてきた改善と挑戦を礎に、埼玉県産業振興公社の連携支援を受けながら、自社の強みを分析し、EV業界などへの進出を視野に新たな市場開拓に挑んでいく。